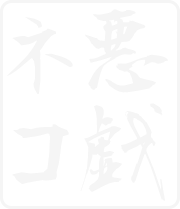ホーム → 文法 → 庭三郎
43. 否 定
43.1 否定の形式と用法
43.2 二重否定
43.3 否定でないもの
43.4 その他のこと
43.1 否定の形式と用法
43.1.1 否定の形式
43.1.2 否定の範囲・焦点
43.1.3 部分否定
43.1.4 否定と副詞
43.2 二重否定
43.2.1 〜ナイ(トイウ)コトハ/モナイ
43.2.2 〜ナクハ/モ ナイ
43.2.3 V−ナイデハナイ
「否定」をムードに入れるかどうかは、「疑問」以上に疑問となるところで
す。もちろん、ごくふつうの否定文にある種のムードがあるのは確かですが、
それを「否定のムード」と言っていいのかどうかはわかりません。例えば、
これは私の本ではありません。
という文には、はっきりと「否定」する話し手の気持ちがあります。しかし、
それは結局のところ肯定の場合と同じ種類のものだとも考えられるので、この
本では「38. 断定・確信」のところで、肯定文も否定文もとりあげました。
すると、否定独自のムードとは何か、が問題になります。結局は、「ムード
とは何か」ということがはっきりしないことが問題の基本にあるのです。
さて、そういう議論はともかくとして、否定についてまとめておきます。
43.1 否定の形式と用法
43.1.1 否定の形式
否定の形式には、次のようなものがあります。「ぬ」を使った文型はこの本
ではとりあげませんでした。「ぬ」はもちろん「ない」の古典語です。現代語
ではごく限られた慣用的表現の中で使われます。「ず・ざる・ね」は「ぬ」の
活用形とされます。
ない 私のではない 大きく(は)ない 読まない
ません 私のではありません 大きく(は)ありません
読みません
ず 読まず(に) (→「47.並列」)
ざる 読まざるを得ない (→「36.義務・必然・不必要」)
ぬ 知らぬ存ぜぬ 知らぬ間(ま)に(知らない間に)
ね 知らねばならぬこと(知らなければならないこと)
では、否定に関するいくつかの用法を見てみましょう。まず、何が否定され
ているのか、ということから。
43.1.2 否定の範囲・焦点
否定文とは、何を否定しているのか。当たり前のようで、難しい問題をはら
んでいます。これは「疑問」の場合とよく似ています。例えば、
「食べますか」「いいえ、食べません」
のような場合なら、述語の否定ということではっきりするのですが、次の例で
はそうかんたんではありません。
彼女は速く走らなかった。
車で来ないで下さい。
この「走らなかった」「来ないで」の「ない」は、「走った」ことや「来る」
ことを否定しているのではありません。否定されているのは「速く」や「車で」
の部分です。
否定を使わないで別の言い方をするとすれば、上の例は、
彼女はゆっくり走った。
電車やバスで来て下さい。
ということができます。
ここで、「速く走る」全体が否定されているのだと言うこともできます。否
定の「ない」が「走る」に接続しているのは事実ですから、そのこととつじつ
まを合わせるためには、副詞を含めた動詞句全体にかかると言えばいいことに
なります。
しかし、その場合には、
速く走らない → ゆっくり走る
であることをどう説明するのかが問題になります。「ない」が意味的には「速
く」にかかるのだと考えれば、
(速く+ない)走る → (ゆっくり)走る
というのはわかりやすい考え方です。「車で」の例も、
(車で+ない)来て下さい → (電車やバスで)来て下さい
と考えればいいわけです。
以上のことを、「速く走る」は「ない」という否定のかかる「範囲」であり、
その中で「速く」は否定の「焦点」になっている、という言い方をします。
たぶん速く走らないだろう。
の場合は、「たぶん」は否定の範囲の外にあると考えます。「速く走らない」
ということが、「たぶん・・・だろう」という推量の内容になるからです。
否定の範囲をはっきり示すのが、「は」です。
昨日は学校へ行かなかった。(他の日は行った)
私は昨日は学校へ行かなかった。(他の人/他の日は行った)
あとの例は、「田中さんは昨日学校へ行ったが」という文脈なら、「私」が、
「私はいつも学校へ行くが」という文脈なら「昨日」が焦点となります。
佐藤さんとは一緒に行きません。
車では来ないで下さい。
速くは走らなかった。
「数量詞+は/も+ない」の形については、「副助詞」のところでとりあげ
ました。なかなか微妙な意味になります。(→「18.13 Nは」
百人はこない。
百人も来ない。
43.1.3 部分否定
否定が数量・頻度や程度の表現と共に使われると、その解釈が問題になりま
す。
毎日休まなかった。(ぜんぜん休まなかった)
毎日は休まなかった。(休みが多かったが、時々行った)
これらははっきり違います。全部が否定されるものを「全部否定」、一部が
否定されるものを「部分否定」と呼ぶことにします。
前の例の図式にならって考えると、全部否定のほうは
(毎日)(休まなかった)
のように考えられます。「ない」は「休む」だけにかかります。「休まない」
ということが「毎日」起こったのです。
部分否定の例は、
(毎日+ない)休む
と考えられます。「ない」が述語以外を焦点とする場合、その焦点を示すため
に「は」が使われているのです。
次の例では「は」があってもだいたい同じです。
よく調べなかった。
よくは調べなかった。
どちらも一応は調べていますが、「よく」ではありません。
最後まで読まなかった。
この例は微妙で、二つの意味になります。
ある文章の「途中まで読んだ(後半は読まなかった)」という意味と、もう
一つは時間的な意味で、「読まない状態を最後まで続けた」という意味です。
どこを強めて言うかにも影響されるようです。「まで」に「は」を付けると、
はっきり前者の意味に落ち着きます。
最後までは読まなかった。(最後の部分は読まなかった)
「は」や「も」は述語の内部にも入ります。これは副助詞のところでもとり
あげました。
殺さない。
殺しはしない。ちょっと痛めつけるだけだ。
重くはないが、軽くもない。
高くはないが、安くは/も ない。
「V−はしない」の形は、動詞の意味を否定しながら、それに近い何かを暗
示します。
「〜のではない/わけではない」は、「部分否定」とは違いますが、全面的
な否定ではない、という意味では近い用法です。
1 資料を全部見たの/わけ ではない。
2 この事典を調べたのではない。
cf. この事典は調べなかった。
例1では、部分否定になっていますが、例2では他の何かと対比しているよ
うに感じます。
複文で理由などを表す節があると、「〜のではない」の否定はその節を焦点
とします。
金が欲しいから行ったのではない。
「行った」のですが、その理由は「金が欲しいから」ではない、ということに
なります。
43.1.4 否定と副詞
副詞の中には否定と共に使われるものが多くあります。
ぜんぜん さっぱり まるで ちっとも
ほとんど 少しも ろくに たいして
「ろくに」「たいして」は連体詞の形もあります。
ろくに/たいして 調査しなかった。
ろくな/たいした 調査をしなかった。
すでに触れたように「よく〜ない」は部分否定を表し、「は」をつけても使
われます。
よく見なかった。
よくは見なかった。
「十分に」も同じような用法になります。
十分に活動できた。
十分に(は)活動できなかった。
けれども、一般に副詞が否定とともに使われると「+は〜ない」という形で
部分否定を表すわけではありません。
「とても・かなり・非常に」などの程度副詞は「は」がつきません。
とても面白くなかった。(部分否定ではない)
?とてもは面白くなかった。
「ほとんど」は「は」をつけても部分否定にはなりません。
ほとんどわかった。
ほとんどわからなかった。 (ほんの少しわかった)
ほとんどはわからなかった。( 〃 )
次の例は複文ですが、「あまり〜ない」のかかり方の解釈が難しい例です。
あまり力を入れて握らないでください。
の「あまり」は「あまり・・・握らないで」ではなく、「あまり力を入れないで」
の意味です。つまり、「力を入れて握らない」のは「握らない」のではなくて、
「力を入れない+握る」という意味だからです。
副詞ではありませんが、不定語の「何も」や、「1+数量詞+も」(一人も)
が否定とともに使われるということは、それぞれのところで述べました。
43.2 二重否定
否定の形式が重なって使われることがよくあります。学習者にとって、瞬間
的に理解するのが難しいものです。
まず、形式名詞の前後に否定の形式が来ることがあります。これはこれまで
にもいくつも出てきました。
知らないわけが/は ない (知っているにちがいない)
知らないはずが/は ない ( 〃 )
食べないわけには/も いかない(食べなければならない)
食べないわけでは/も ない (いちおう食べる)
上のかっこの中に出てきた「〜なければ/なくては ならない/いけない」
も形の上では二重否定ですが、教える場合はそのことに注目させる必要はない
でしょう。
以上の他に、以下のような二重否定の文型があります。だいたいは「少し〜」
とか「一応は〜」のような意味合いを表します。「〜ないわけではない」と近
い意味です。
43.2.1 〜ない(という)ことは/も ない
名詞節の「〜こと」を使った文型です。「〜ことがある」の否定のようです
が、そうではありません。
論理学も、興味がないことはありません。(少しはある)
×興味がないことがある
「興味がない場合がある」という意味とすれば、別の文型です。(→ )
(ふだんは興味があるが、)時々興味が(持て)ないことがある。
否定を否定して、「少しは、一応」などの肯定的意味になります。「〜が/
けど、〜」などの逆接で受けて、後に否定的な内容が続くことも多いです。
まあ、うれしくないことはない。(少しうれしい)
一人でもやってやれないということはありません。(一応できる)
テニスですか?できないことはないけど、うまくはありません。
ウオッカは、飲まないことはないが、好きじゃない。
そう言えないこともない。(そう言える面もある)
明日?まあ、暇じゃないこともない。(暇だと言える)
君の主張も、わからないこともないんだけどね。(一理はあるが)
何かを強く肯定したいような場合、二重否定が現れます。これは「〜も」で
は言えません。
これがわからない?こんなやさしい問題がわからないということは
ないだろう。(×〜ということもないだろう)
あの人が来ないということは(絶対)ないと思いますよ。
なお、「という」については「56.連体節」「57.名詞節」を見てください。
次の例は、「〜ないことがある」の否定で、この文型とは違います。
あの人は、集合時間に遅れて来ないことはないんです。(いつも遅
れて来る)
彼女の会計は、計算が合わないことはない。(いつも合う)
また、次の例は「内の関係」の連体節で、その下の例と同じ文型です。
彼女はおよそ万能で、できないことはありません。(何でもできる)
(ある)ことができない → できないこと(はない)
彼はゲテモノ好きで、食べられない物はない。(何でも食べられる)
43.2.2 〜なくは/も ない
述語の否定形にさらに「ない」がつき、そこに副助詞の「は・も」が割り込
んだ形です。「〜ないこともない」と同じような意味合いです。
その話も、信じられなくはない。ありそうなことだ。
そうか。そういうふうに言えなくもないね。
この写真は、色っぽくなくもないが、今一つだね。
時間は多少なくはないが、そんなにとれないよ。
43.2.3 V−ないでは/も ない
動詞の否定形に「ではない」がつくという特別な形です。あとには否定的な
内容が来ます。これも同じような意味合いです。
君の気持ちも分からないではない。だが、ここは我慢してくれ。
相手の事情も知らないではないが、引き下がるわけにはいかない。
その種の番組は、見ないでもないが、あまり興味はない。
ずいぶんいいお話だと思わないでもありませんが、ちょっと・・・。
見てみたいという気がしないでもないが、まあやめておこう。
二重否定の形を使って、柔らかく、あるいはあいまいに自分の考えを述べる
というのは、いかにも「日本的」表現だと言われそうなところですが、案外他
の言語でもやっていることかもしれません。それにしても、似たような形がい
くつもあるのは学習者にとっては、そして日本語教師にとっても、迷惑な話で
す。
複文、特に「引用」の場合に二重否定が問題になりますが、それは引用のと
ころでとりあげます。
43.3 否定でないもの
否定の形を使いながら、否定の意味を持たない文型があります。学習者にと
って注意が必要なものです。
これまでにとりあげた文型では、勧誘の「V−ないか」がそれにあたります。
散歩に行かないか。
もう一つ召し上がりませんか。
主体である聞き手の意志的動作を表す動詞の現在形の否定形が使われます。
これは比較的わかりやすい用法でしょう。
願望の「V−ないかなあ」(→37.3)も否定形を使いながら、否定の意味はあ
りません。「〜ないものか」(→40.2)も同じです。
確認の「〜(ん)じゃないか」(→40.4)もここに入れられます。
43.4 その他のこと
否定に関する小さな問題を二つ。
[否定の応答]
「はい」に対応するのはもちろん「いいえ/いえ」ですが、ほかに「いや」
「ううん」があります。「いや」はくだけた言い方で、おもに男性のことばで
す。それにたいする女性のことばは「いえ」でしょうか。「いや」は書きこと
ばで、
問題はそこにあるのだろうか。いや、そうではないだろう。
のような自問自答にも使われます。
話しことばでは「ううん」という形もよく使われます。「いいえ」は実はか
なり改まった表現で、親しい間柄では使われません。例えば小さい子どもが母
親に使うと変でしょう。その代わりに「ううん」が使われます。この形はなぜ
か国語辞書には載っていないことが多いのですが。
[ナシ]
これは文法の問題とは言えませんが、「ない」の代わりに「なし」という語
を使うことがあります。
特に問題なし。
特に、履歴書などの書類に使います。
賞罰 なし
これを「ない」と書くのは何とも変です。
なお、否定と他のムードとの関係は次の「複合述語のまとめ」で触れること
にします。
[否定を表す接頭辞]
否定は文の述語だけでなく、単語によっても表されます。
この町の人は親切ではない。
この町の人は不親切だ。
「親切・不親切」はどちらもナ形容詞ですが、品詞が変わる例もあります。
その考え方は合理的ではない。
その考え方は不合理だ。
参考文献
工藤真由美2000「否定の表現」『時・否定と取り立て』岩波書店
カノックワン・ラオハプラナキット「疑問文文末形式「否定辞+カ」の意味と用法」
工藤真由美1997「否定文とディスコース−「〜ノデハナイ」と「〜ワケデハナイ」−」『ことばの科学』むぎ書房
杉村泰1998*「否定構文に現れる副詞とモダリティ」『ことばの科学』11名古屋大学言語文化部言語文化研究会
野田春美1995「〜ハ〜ナイ、〜シハシナイ、〜ノデハナイ、〜ワケデハナイ」宮島他編『類義上』くろしお出版
山中美恵子1993「限定と否定」『日本語教育』79
ルチラ パリハワダナ1994「否定から見た文階層構造」『日本語学科年報』16東京外国語大学
Naomi Hanaoka McGloin「Negation」