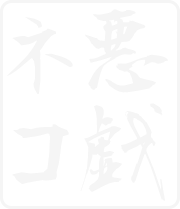ホーム → 文法 → 庭三郎
51.目 的
51.1 V−に
51.2 V−ため(に)
51.3 V−のに
51.4 V−には
51.5 〜よう(に)
51.6 「は」と「が」
51.2 V−ため(に)
[疑問・否定] [V-(ん)がために] [V-に/V-ために] [V-ためには]
51.5 〜よう(に)
[V-のに〜ように(するために)]
あること・状態Aが実現することを目指して、何らかの行動Bをする時、そ
のAをBの「目的」と言います。主節Bは意志的な動作を表します。
目的を表す表現としては、次の四つが代表的なものです。
本屋へ本を買いに行きます。
大学に入るために、勉強しています。
学校へ通うのに、自転車が必要です。
遅れないように、急いで行きました。
上の4つの表現は、それぞれ使い方が違います。その使い分けを考えてみま
しょう。
51.1 V−に+移動動詞
兄は駅前の本屋へ辞書を買いに行きました。
「V−に」と動詞の間に他の要素が入ってもかまいません。
兄は辞書を買いに駅前の本屋へ行きました。
「本を買う」ことが目的で、「本屋へ行く」のです。語順はどちらでも言え
ますが、日本語教科書の例文は前の型が多いようです。「V−に+動詞」で一
つのまとまりのように感じられ、複合述語のようですが、間に他の要素を入れ
ても問題はありません。
ただ、あまり長くなると、目的節と動詞とのつながりが切れてしまうので、
「ために」のようなはっきりした形式が使われます。
方向性を持つ移動動詞だけに使われる文型で、その点は分かりやすいと言え
ます。動詞の形は中立形ですので、学習者にとっても覚えやすい文型です。
手紙を出しに郵便局へ行きました。
タクシーを呼びに行きましょうか。
彼女はそのことを知らせに来たんですか。
部屋へ忘れ物を取りに戻った。
母は、買い物に出かけて、留守ですが・・・。
忙しくて、遊びに行けませんでした。
節の中の動詞が「スル動詞」の場合は、
川へ洗濯をしに行く。
川へ洗濯しに行く。
川へ洗濯に行く。
の三つの言い方ができます。最後の形がいちばんよく使われるでしょう。形の
上では「名詞+に」になっていて、補語のようです。ただし、「所へ」を動詞
の前に持って行くと落ち着きません。
?洗濯に川へ行く/散歩に公園へ行く/見学に工場へ行く
「散歩に行く」「見学に行く」などがまとまって一つの動詞のようになり、そ
れが「所へ」をとっていると考えられます。
「スル動詞」の名詞以外でも、この形になるものがあります。
ゴルフに行く。
の場合、「×ゴルフする」は正しい言い方とは言えませんが、「ゴルフをする」
なら言えるので、「スル動詞」に準ずるものと言えます。
医者に行かなければならない。
映画/コンサート に行こう。
「医者」や「映画/コンサート」は「ところ」でもなく、「する」を付けて
動詞にすることもできませんが、「医者に行く」は「病院へ行って医者に診て
もらう」ことを意味し、「映画に行く」は「映画館で映画を見る」ことを意味
します。「医者」はたぶん例外的で、他は催し物を表す名詞です。
×精神科医/カウンセラー/弁護士/税理士 に行く
さて、「〜しに行く」は「行って〜する」と近い意味になります。
図書館へ本を借りに行く。/図書館へ行って本を借りる。
しかし、過去の形にして「〜た」とすると、「借りに行った」と「行って借りた」
では違います。
図書館へ本を借りに行った。(が、その本はなかった)
図書館へ行って本を借りた。(が、帰りになくしてしまった)
図書館で本を借りてきた。 (そして今読んでいる)
「借りに行った」だけでは、本当に「借りた」かどうかはわかりません。「借
りてきた」なら、本当に「借りて」しかも今も持っています。この辺をとっさ
に使い分けるのは、学習者にとって難しいことでしょう。
[疑問と否定]
疑問文も自由に作れます。
こんな夜中に何をしに行くの?
今日はどこへ食べに行こうか。
この例で「?食べにどこへ行こうか」とは言いにくく、「食べに行く」が一
つのまとまりとなっているのがわかります。
目的を否定するためには、「〜のではない」を使います。
金を借りに行かなかった。
とすると、そもそも「行かなかった」ことになります。
金を借りに行ったのではない。
「行った」ことが文脈にあって、「金を借りに」ではなく、他の用事で行っ
たのだ、ということを表します。
51.2 V−ため(に)
「V−ために」は目的を表す形式としていちばん普通のものです。「に」は
省略できますが、少し硬く、書きことば的になります。
弁護士になるために、法律を勉強しています。
食べるために働くのか、働くために食べるのか。
大阪での会議に出席するため、朝の新幹線に乗った。
名詞を受ける場合は、「〜のために」となります。
海外旅行のために、貯金しています。
「(〜のは)〜ためだ」の形で、目的を表す節を主節の位置に持ってくること
もできます。質問の答えとしてよく使われます。
今苦労するのは、後で楽をするためです。
「何のためにお金を貯めているのですか。」「家を買うためです。」
「V−ための」の形で連体修飾できます。
やせるための努力
日本語教師になるための勉強を続けています。
何をするための道具か。
「ために」が受ける動詞は「意志的」な行為か、「ある程度意志的にコント
ロールする」ことができるような現象です。また、その動詞の主体は主節の動
詞の主体と同じです。後で見る「〜ように」との違いです。
否定は、その意味によって受けられるものと受けられないものがあります。
主節の動詞のムードは特に制限がありません。
朝早く起きるために、モーニングコールを頼みました。
太るためにたくさん食べます。
太らないために毎日運動します。
人の命を守るために、基礎医学を研究したい。
地球から戦争をなくすために努力しよう。
事故を起こさないため、速度制限を必ず守って下さい。
×日本語が話せるために、よく練習する。(可能動詞:非意志的)
×大きな花が咲くために、肥料をやる。 (主体が別)
「太らない」ことが「意志的にコントロールできる」ことかどうかには疑問が
残るのですが・・・。
弁護士になるために、法律を勉強しています。
?弁護士になりたいために、法律を勉強しています。
「〜たい」の例は、「〜たい」が意志的な述語でないので、目的としては成
り立たず、理由の意味に解釈されます。
主節の述語は意志動詞がふつうですが、「ある」や「必要だ」なども使えま
す。その場合、「主体が同じ」という制限の例外になります。
大学の図書館というものは、学生が勉強や昼寝に使うためにあるの
で、本を保存・管理するためにあるのではない。
社会人特別入試は、社会人が大学で学び直すために是非必要だ。
[疑問・否定]
目的を問う疑問の形は、理由の「〜から/ので」と同じように「なぜ/どう
して」で聞きますが、そのほかに「何のために」という形があります。
「なぜ/何のために 働くのか」「生きるためです」
「何をするために」とも言えますが、あまり使われないようです。「何のた
めに」で十分だからでしょうか。
何を手に入れるために、そんなにがんばっているんですか。
どんな教育をするために、新しい学科を作るのですか。
否定は3カ所に現れえます。「ため」が受ける述語、目的節、そして主節で
す。
原子力潜水艦を寄港させないために大規模なデモをした。
否定を受けることは、積極的な意味合いさえあれば、別に問題ありません。
?金を貯めるために働いていません。
cf. 生活保護を受けるために、(働けるのに)働いていません。
金を貯めるために働いてはいません。
金を貯めるために働いているのではありません。
その目的でなく、ほかの目的があることを言いたい場合、単に主節の述語を
否定にすると少し安定しません。「は」を入れるか、文末に「〜のではない」
をつけるかすると、目的の否定になります。
目的節自体を否定にするには、「〜ため(に)だ」の形の否定を使います。
ただ生きるため(に)でなく、有意義に生きるために働く。
[V−(ん)がために]
古い言い方で、「V−(ん)がために」という形があります。動詞の形は、
「−ず」に続く形と同じです。
汚名を挽回せんがため、必死に努力した。(挽回するため)
[V−に/V−ために]
「V−に」と「V−ために」とのどちらでも使える場合があります。
彼は新聞を読みに図書館へ行きました。
彼は新聞を読むために図書館へ行きました。
この雑誌を読むために、バスに乗って遠くの町の図書館まで行った
ものです。
この雑誌を読みに、バスに乗って遠くの町の図書館まで行ったもの
です。
「V−に」のほうは、他の語句が間に長く入ると少し安定しませんが、それ
ほど不自然とも言えません。
[V−ためには]
「ために」に「は」が付くと、いろいろな点で違ってきます。まず、主節の
述語のムードが制限されます。
書類を細かく切るためには、この機械を使います。
よい医者になるためには、人間の心を知らなければならない。
自然を守るためには、ムダを抑えることが必要だ。
長生きをするためには、第一に暴飲暴食を慎むことだ。
自然な日本語を話すためには、一度文法を忘れたほうがいい。
以上の例では「ため」を省略して「V−には」の形でも言えますが、次の例
はだめです。
事故を起こさないためには、まず速度をひかえよう。
家族を養っていくためには、どんなことでもした。
「〜なければならない」「〜が必要だ」「〜ことだ」「〜ほうがいい」など
のムードを持つものが多く、この点で、すぐ後に見る「V−のに」とかなり似
ています。
次の例では、「ために」に「対比」の意味の「は」が付いているものと考え
られます。
彼らは警察の追求を避けるためには大金を使い、目撃者を黙らせる
ためには家族を脅した。それでもだめな時には、人を殺すこともた
めらわなかった。
「AためにB」の場合は、Aは動詞ですが、「AためにはB」では「名詞+
である」も使えます。
よい教師であるためには何が必要か。
連体節・名詞節の中では「ために」の形でも使われます。
よい教師であるために必要なものは何か。
よい教師であるために何がいちばん大切か、よくご存じでしょう。
「〜ようにするために」という形があります。これは後の「〜ように」のと
ころでとりあげます。
51.3 V−のに
逆接の「〜のに」とはまったく別の文型です。こちらは、動詞の基本形だけ
を受けます。
これだけ人を集めるのにずいぶん金がかかった。
歯を磨くのに3分かかる。
ご飯を食べるのに箸を使う民族と、手で食べる民族とでは、手先の
器用さに違いがあるだろうか。
こんなにおもちゃを出すと、後で片付けるのに大変だ。
ある名詞を主題としてとりあげ、それについて述べる形でよく使われます。
このはさみは、髪をすくのに使います。
テレビ会議は、時間のムダをなくすのにとても役に立つ。
この避難所は、みんなが集まるのに1時間もかかる。
「のに」に「は」が付いた「のには」という形と、その「の」を省略した「に
は」という形もあります。「にも」という形も使われます。「には」は次でま
たとりあげます。
中国の箸は小さいものをつまむのには不便だ。
駅へ行くには、この道が便利だ。
駅から遠いので、買い物に行くにもひどく不自由している。
動詞の否定は受けられません。
これが、タバコをやめるのにいちばんいいです。
×これが、タバコを吸わないのにいちばんいいです。
この文型の特徴は、主節の述語がかなり限定されていることです。その述語
とは、
かかる・要る・必要だ・大切だ・便利だ・不便だ・役に立つ・いい
・使う・利用する・苦労する
などです。
これらの述語は、名詞をとるときも、「名詞+に」をとります。
歯磨きに3分かかる。
通学には、この道が便利だ。
中国の箸は、豆腐料理には不便だ。
このナイフは、細かい細工に使う。
そこで、この「のに」は、名詞節を作るための「の」と、もともと述語が要
求する「に」が一つになったものと考えることができます。(逆接の「のに」
は述語が制限されないので、同じように考えることはできません。)
ただし、次のような例外もあり、どう考えたらいいかわかりません。
この箱は、本を詰めて送るのにとっておいてください。
それを縛るのに、ひもを何本か置いてあります。
それは、要らないものを入れるのにあげたんです。
これらの動詞は、「名詞+に」の形で、「?郵送にとっておく」「?梱包に
置く/あげる」などとは言えないでしょう。
51.4 V−には
「〜には」は「〜のには」の「の」が省略されたものと考えます。「〜ため
には」に似ていますが、否定が受けられないことや、次の最後の例が言えない
ところが違います。
日本語が上手になる には/ためには、どうしたらいいでしょうか。
やせるには、まず食べ過ぎないことが大切です。
×太らないには、まず食べ過ぎないことが大切です。
失敗しないためには、どんなことに気をつければいいですか。
×失敗しないには、〜
×失敗しないのには、〜
試験に受かるためには、どんなことでもします。
×試験に受かるには、〜
また、次のような例があります。
この服は、私が着るにはちょっと小さいですね。
この家は、夫婦二人で住むには広すぎる。
この場合は、「目的」というより、「評価の基準」の意味になっています。
あとで「57.名詞節」でとりあげる「難易」を表す述語もこの「V−には」
の形になります。こちらも「V−には」の部分が基準になっています。
この問題は、中学生にやらせるには難しすぎる。
51.5 〜ように
「〜ように」も「目的」を表すと言われることがありますが、少し違うよう
です。「に」を省略して「〜よう」だけでも使えます。少し硬い言い方になり
ます。
早く起きられるように目覚ましをかけた。
漢字が覚えられるように風呂場に漢字表を貼った。
よく聞こえるように音を大きくした。
間違えないように慎重に記入してください。
倒れないように台をしっかり押えてください。
犬が入ってこないように門を閉めた。
「目的」ではなく、「目標」だとする人もいます。Aとなることをねらって
ある動作Bをするのですが、Bの動作が直接Aを引き起こさないというのです。
「V−ために」との使い分けが常に問題になります。
―沼粟瓩瞭飴譴亮臑里函⊆臉瓩瞭飴譴亮臑里違う場合は、「ために」は使
えません。上の例文の最後の2つもこの例です。
風が入るように窓を大きく開けた。(×ために)
子供がたくさん食べるように、料理を工夫する。
少しでも学生が進んで勉強するように教科書を編集しました。
◆―沼粟瓩瞭飴譴可能動詞・無意志動詞の場合、「ように」が使われます。
否定形の場合も「ように」が多く使われます。主節の主体による「コントロ
ール」が可能なことかどうか、が使い分けの条件だと言われます。初めにあ
げた例文の4つめまではこの例です。
よく眠れるように、部屋を暗くして昼寝をしました。(×ために)
「ために」と両方が使える例。
太らないように/ために 甘いものをひかえています。
太るように/ために 夜中に間食しています。
「ように」は、従属節の述語が動詞以外でも使えることがあります。
いつでも使用が可能なように調整してあります。(可能だ)
持ち運びに便利なように取っ手が付いている。 (便利だ)
待合室が寒くないように新しい暖房をつけた。(寒くない)
子供たちが楽しいように、いろいろな遊具を揃えた。(楽しい)
「〜ように」と共によく使われる動詞があります。
いい教師になれるようがんばります。
ご期待に添えるよう努力します。
もっと形式的な動詞として「する」があります。
これからは飲み過ぎないようにします。
ひもを掛けて、荷物が落ちないようにします。
「V−て、〜ようにする」は、「〜ように、V」の形に変えられます。
荷物が落ちないように、ひもを掛けます。
ここに網戸をつけて、風が入るようにしよう。
風が入るように、ここに網戸をつけよう。
「〜ように」は他の目的の表現とは性質が違うため、ともに使える場合があ
ります。「〜ようにするために」はよくある形です。
虫が入らないようにするため、網戸を取り付けさせた。
中がよく見えるようにするために、ガラス部分を大きくするなど、
様々な設計変更をした。
「〜ように」とは「〜ようにするために」の省略形だとする説もあります。
[V−のに〜ように(するために)]
ゴミを取り除くのに都合がいい/便利な ように工夫がしてある。
お風呂をわかすのに時間がかからないように太陽熱利用装置を付け
ました。
持ち運ぶのに便利なようにするために、箱に取っ手をつけさせた。
この例のように「のに・ように・ために」を全部使うこともできます。
51.6 「は」と「が」
同一の主体で、「Nは」で示される場合は問題ありません。「〜ように」の
場合に、動詞の意志性が問題になるくらいです。
「Nが」の例は少ないでしょうが、可能です。
田中さんが、本を借りに図書館へ行った。
兄が、司法試験を受けるために、突然、猛勉強を始めた。
父が、本を読むのに老眼鏡をかけるようになった。そんな年なんだ。
主体が違う場合、従属節は「Nが」になります。
次のような「は」は現れます。
彼にはわからないように彼女が鍵を隠したんです。
参考文献
青山文啓1995「ある複文の中の助動詞」『阪田雪子先生古稀記念論文集 日本語と日本語教育』三省堂
于日平「「タメニ」の意味表出と構文的特徴−複文に見られる時間関係と意志性について−」不明・紀要
奥津敬一郎「形式副詞論序説−「タメ」を中心として−」
高橋友子「「ため」の用法−その一考察」
北條淳子1986「初級後半における文型指導の実際−目的を表す文型を中心に−」『講座日本語教育』22早稲田大学
佐治圭三「類義表現分析の一方法−目的を表す言い方を例として−」金田一春彦古稀記念
塩入すみ1995「スルタメニとスルタメニハ」宮島他編『類義下』くろしお出版
鈴藤「「覚え書き」から 「目的」を表す「ために」と「ように」」」学友会?
前田直子1993「「目的」を表す従属節「〜するように」の意味・用法−様態用法から結果目的用法へ」『日本語教育』79
前田直子1993「「目的」を表す従属節「〜するように」の意味・用法−様態用法から結果目的用法へ」『日本語教育』79
前田直子1995「スルタメ(ニ)、スルヨウ(ニ)、シニ、スルノニ」宮島他編『類義下』くろしお出版
益岡隆志 2001「複文の意味分析−目的表現をめぐって」『国文学』2001.10学燈社